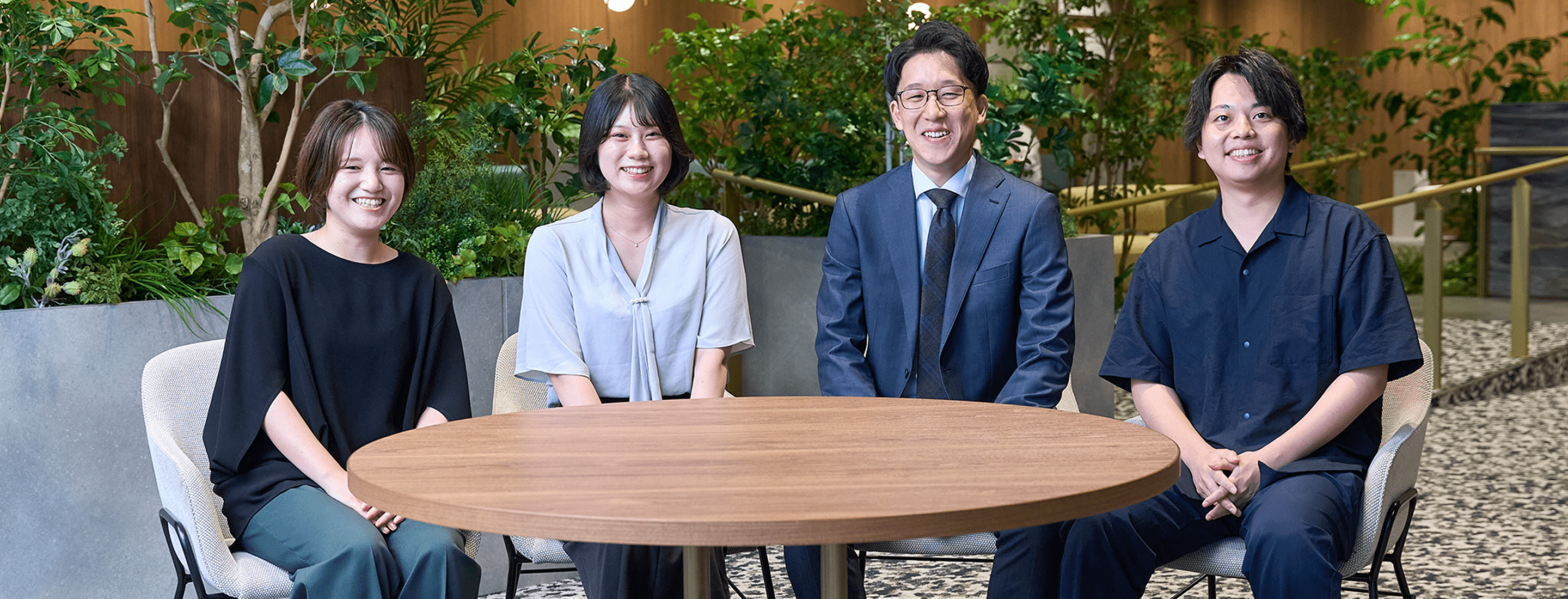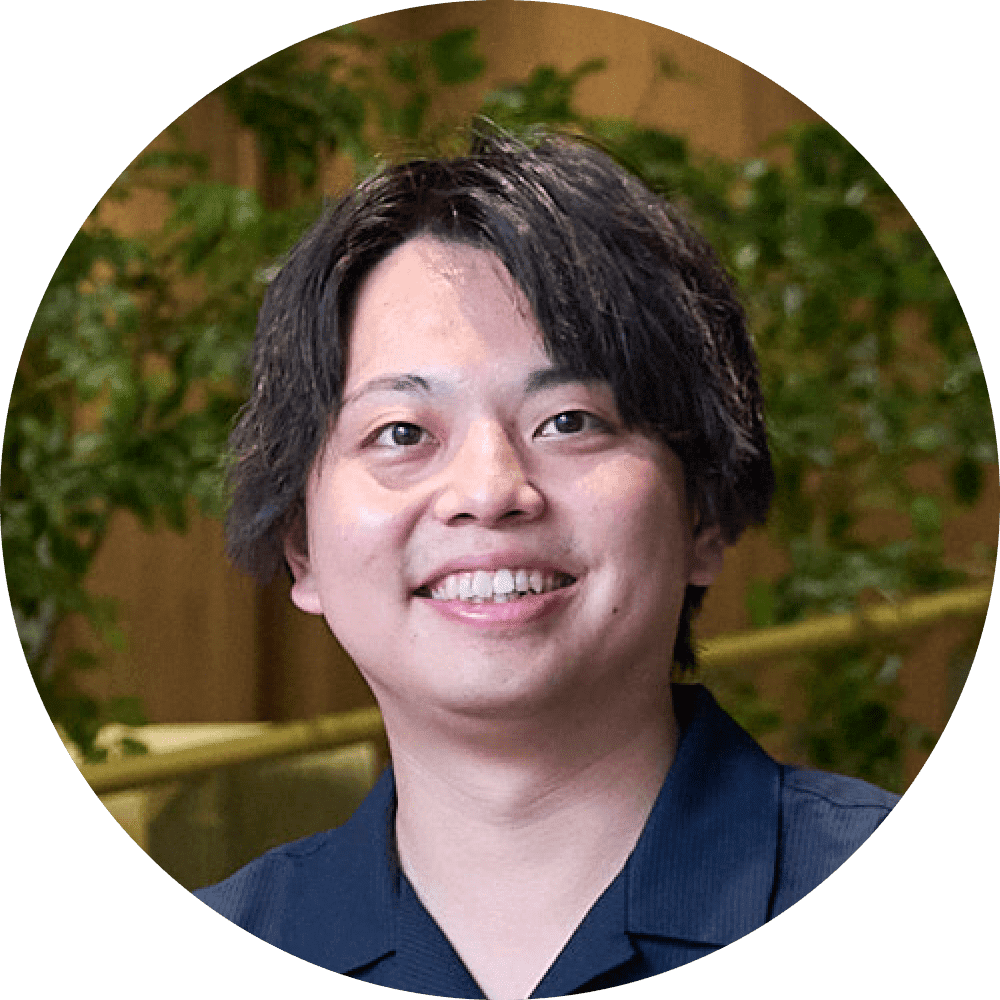Q
新人研修はどうでしたか?
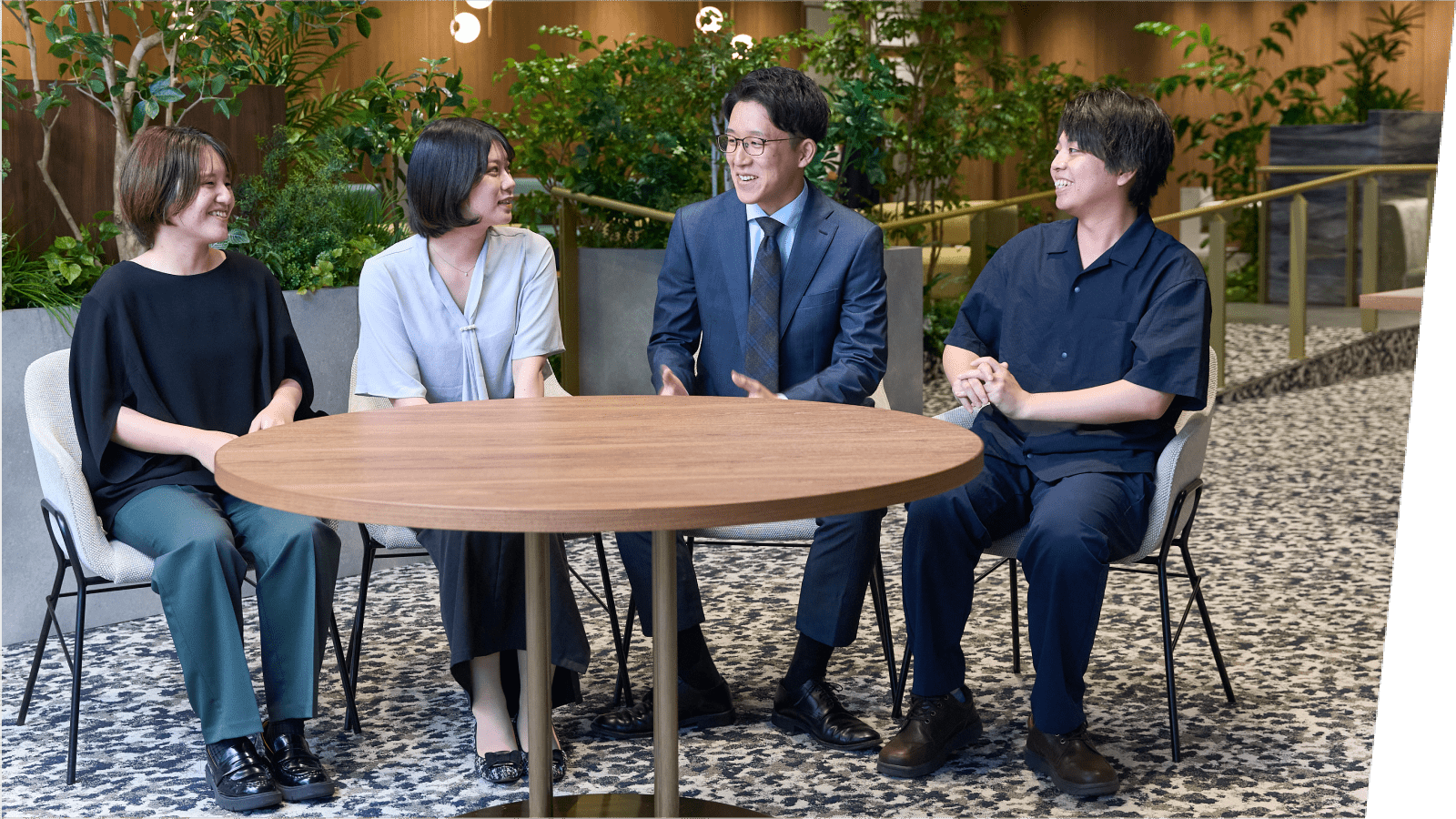
水高森トラストの新人研修の最も大きな特徴は、1年間で3部署(2024年入社以降は半年で3部署)に配属される「3部署にローテーション」だと思うけれど、どうだった?
下條3部署ローテーションでは事業推進部、広報・マーケティング部、総務グループを経験しました。当時は業務内容や環境の変化が目まぐるしく大変でしたが、今振り返ると、新規事業やオフィス物件のことなど本当に様々なことを勉強できた1年だったなと思います。事業のことはもちろん、会社の「人」も知れる点がこの制度の良いところですね。
佐々木部署によってカラーは変わった?
下條もちろん部署によって業務内容や業務の進め方は異なりましたが、私の場合どれも若手が多いという点では比較的カラーが似ている部署だったかもしれません。どの部署にもOJT(3部署ローテーションで配属された新人をサポートする、各部署の先輩社員)や研修インストラクター(1年間、新人全員の研修を指導・サポートする複数人の社員)の先輩がいたので、日々業務について相談や質問をしながら取り組んでいました。
中村事業推進部ではハーブティー事業に取り組み、広報・マーケティング部では社内広報誌でハーブティーを取材していたよね。事業を進めた側とそれをPRする側という両面で商品を扱うことが出来ていたのは、ローテーション制度ならではだよね。
下條本配属制度のみだったら出来なかったことだと思います。事業推進部でハーブティーをどのように社内外に訴求していくかを検討していた中で、広報・マーケティング部でそれを1つ形にできたというのは自分にとってとても嬉しいことでした。社内広報誌を書くにあたっては、内容の検討から、企画書作成、各種調整まで一貫して任せていただいたので、研修中ながら大きな達成感を感じました。
Q
OJTの先輩から見た
3部署ローテーションはどうですか。
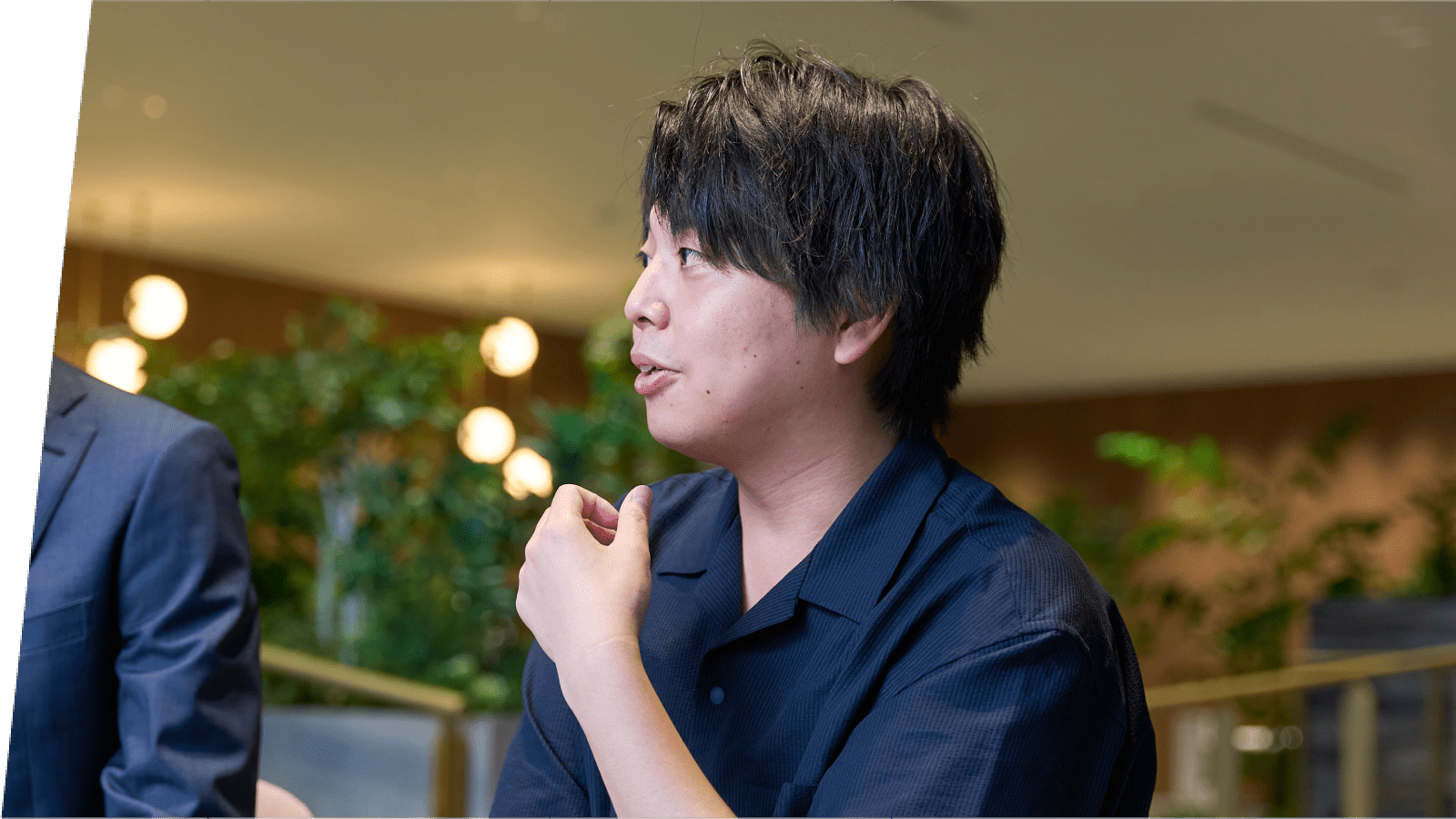
中村ローテーションを見守っていて、社会人1年目の成長度合いはすごいと思った。前半のローテーションでは、社会人として何も知らない状態で来るけれど、だんだんと自分の意見が言えるようになったり皆の情報処理能力が上がっているのが伝わってきたんだよね。
そしてローテーションが切り替わる時は、新人自身がそのローテーション期間に行った業務を、次にその部署に配属される新人に「引継ぎ」を行うけど、あれも非常に大事で。教えることで自身の成果を振り返る機会になったり、相手に誤解なく教えられるかという伝え方の訓練になったり、凄く良い制度だなと思った。
水高OJTとしてはローテーションの限られた期間の中で、部署のことを可能な限り知ってほしいし、何か1つ成し遂げてほしいという思いで取り組んでいるかも。ローテーション期間に、どんな内容でどのくらいの業務を振るか考えるのは難しいけれど、それをするにあたってOJT側も部署のことをより理解しないといけないから、こちら側も勉強になっていると感じるな。
Q
どの研修が一番勉強になりましたか?
特に記憶に残っているものがあれば
教えてください。
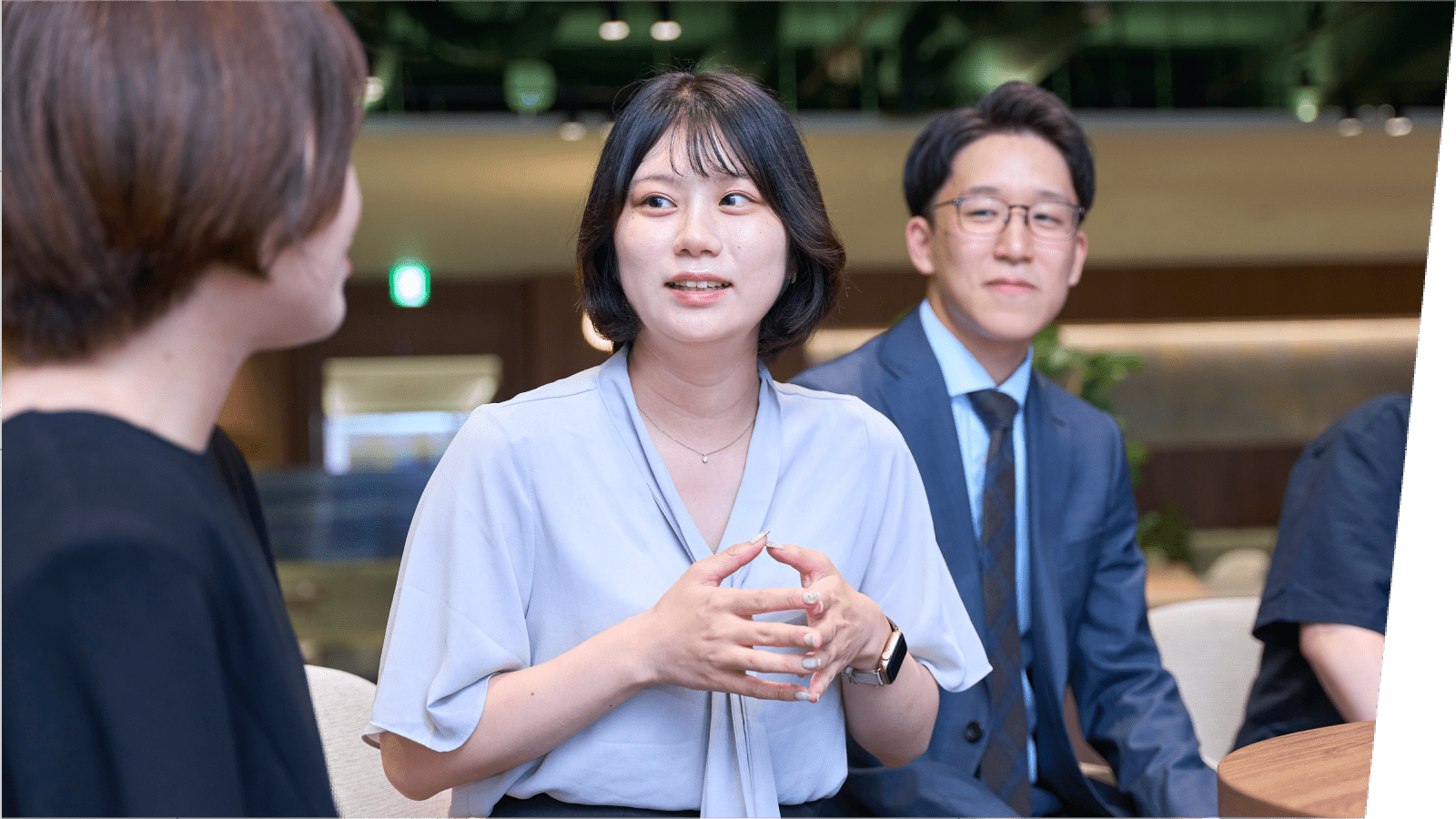
下條3部署ローテーションの他にも複数の研修を経験し、どれか1つを選ぶのは難しいですが…。
プレゼン研修は、プレゼンが非常に苦手だった自分の成長を辿ることが出来たと思っています。
佐々木新人に与えられる1つのテーマに沿って、それぞれが2か月程でプレゼン内容の立案から発表まで実施する研修だよね。最初のうちは悩む部分も多そうで、沢山相談し合ったけれど、日が経つごとにどんどん良くなっていたよ!
水高新本社に変わってワンフロアになったことによって、新人研修をオープンな環境でできるようになったから、新人でも思っていることを多くの社員に発信できる仕組みが出来たよね。大勢に対して発表する場数も踏めるし。
下條提案したい内容について自分で調査・分析すること自体が勉強になったというのももちろんありますが、社会人になってもプレゼン力を養う機会があること、毎回社員の方々からFBや反応を頂けたということは非常に糧になりました。
中村1年のうちに4回もプレゼンする機会があるもんね!
下條最後の卒業研究で社長の前で発表するときには、これまでで1番堂々とプレゼンできたんです。4回のプレゼンを通じて最初の発表よりも自信がついたのもあると思いますね。
Q
インストラクター(1年間、新人全員の
研修を
指導・サポートする複数人の社員)
を担当した3名はどうでしたか。

中村大変だったけれど、楽しかった!水高と佐々木は、自身が新人として研修を受けた次の年(2年目の時)にはインストラクターになっていたけれど、どうだった?
佐々木記憶の新しいうちだったので、やりやすかった部分はありますね。自分の専門外のことを相談されるのは難しかったけれど、自分が新人の時は、背中を押してもらったことが勇気に繋がったから、今度は私がその役に徹しようと思ってやっていました。
ただ、本社移転してすぐだったから、どのスペースをどう使うかなどを0ベースで考えないといけなくて、それは大変でしたよね(笑)。
水高私としては、新人の皆に「こうなっていってほしいな」という思いで色々企画考えるのが面白かったですね。当時2年目ということで、知識量や経験面のサポートは先輩インストラクターに委ねていましたが、「近い距離で一緒に考え、一緒に悩む」という部分は2年目だからこそ出来ると思って取り組んでいました。
下條どのインストラクターの先輩も、自分が提案したい内容について背中を押してくださりながらも、これまでの経験や会社・事業への知見を踏まえて、より良いものになるように軌道修正してくださいました。
特に年次がより近い先輩は、時代の流れに沿って提案の内容やトレンドも変わる中で、自分の提案に関する情報感覚も近かったので、相談しやすかったです。
中村良かった!新人皆個性があって、考え方・プレゼン手法・業務の進め方など千差万別で、その個性を縛らないようにと思っていたんだよね。手取り足取り教えすぎると、先輩をコピーしただけになってしまうし。
逆に新人を見ていて、自分では思いつかなかった色んなやり方があることを学ばせてもらっていたよ。
佐々木同感です!人の悩みにコミットするというのが、やっていて楽しかったですね。
Q
仕事における若手の裁量権は
どんなかんじですか?
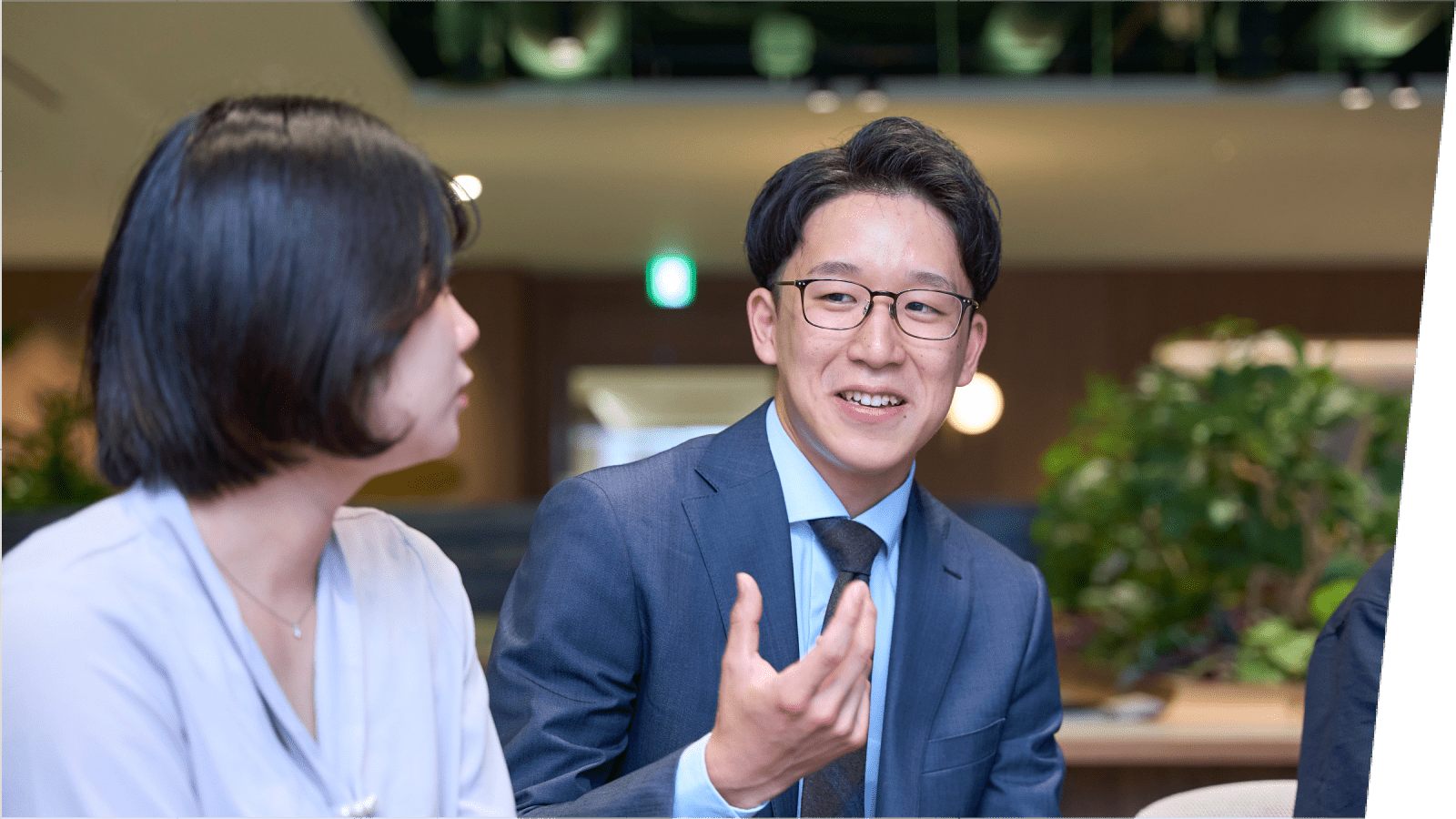
水高渉外グループでは、管理部門における本社担当として、若手であってもビルごとに一人でメイン担当を任せてもらっているよ。管理部門は、他のグループも含め若手が主担当になっていることが多くて、裁量権はあると言えるかな。
テナントの方からしたらビルの代表者は自分だから、年齢を言い訳にせず、しっかり対応していかなきゃと思って取り組んでいるけれど、常にマネージャーや上司が指導・サポートしてくださっているから、安心して仕事に取り決めている!
ファシリティマネジメント部はどう?
佐々木一言で言うと裁量権がありすぎる!本配属されたのは3月だったけれど、3か月後には自分がリーダーとして1つのプロジェクトを回すということをさせてもらって…。ファシリティマネジメント部は内装工事のマネジメントを行う部署で工事が円滑に進むよう工程調整を担ったり、お客さんとのやり取りも自分が中心となって進めたり。相手先の規模によっては社長さんと仲良くなって、二人三脚で決めてたなんてこともあったよ。
裁量権が大きくて良かったことは、工事が終わった後に感謝してもらえること。進める中で色々なことが起きるけれど、その感謝が忘れられず、頑張り続けられているかな。
中村感謝って本当にモチベーションになるよね。私の場合は、広報・マーケティング部のCo-creation(森トラストで行っているエリアマネジメント)チームに所属していて、チームで唯一Co-creation業務だけを行う専任扱い。他のチームメンバーは部内の別業務との兼任者ばかりなので、自分が森トラストのCo-creationの顔にならなければという想いでいるよ。
ただ、エリアマネジメントは正解の無い分野なので、方針や戦略、それらに基づいて実際何をするのかまで全て自分で決める必要があるから、自分が仕事を作り、自分で進めていかないとなにも始まらない。タフではあるけど、街の人の楽しそうな姿を見たり、イベントやニュースなどで形になっているのを見ると、やりがいを感じられるよ。

下條自分で進めていくという点は似ているかもしれません。私の所属する審査室では社内手続きの審査を行っているのですが、そもそも2年目の私に、重要な社内審査を任せてくださっていることからも、裁量権があるなと感じられます。なかなか若手が経験できることではないですよね。自分から他部署のマネージャー層の方々にコミュニケーションを取りに行く場面もしばしばあるので、信頼される人材になれるように頑張っています。もちろん、困ったことがあったら上司に何でも相談できる環境なので、安心して業務に取り組むことができています。
水高以前まで経験を積んだ人が特定の部署に行く流れがあったけれど、今は若手も様々な部署に入れる風潮になったからこそ学ぶべきことは多い分、大きなことを任せてもらえるから、意欲も湧くし成長に繋がっていると思うよね。
下條本当にそう思います。審査に回ってくる手続き書類は各部署が行うプロジェクトなど会社として大事な決定の1つが書かれているので、その書類を審査する業務は会社全体を見渡すという意味で非常に勉強になります。

Q
プライベートで
若手同士の交流はありますか?
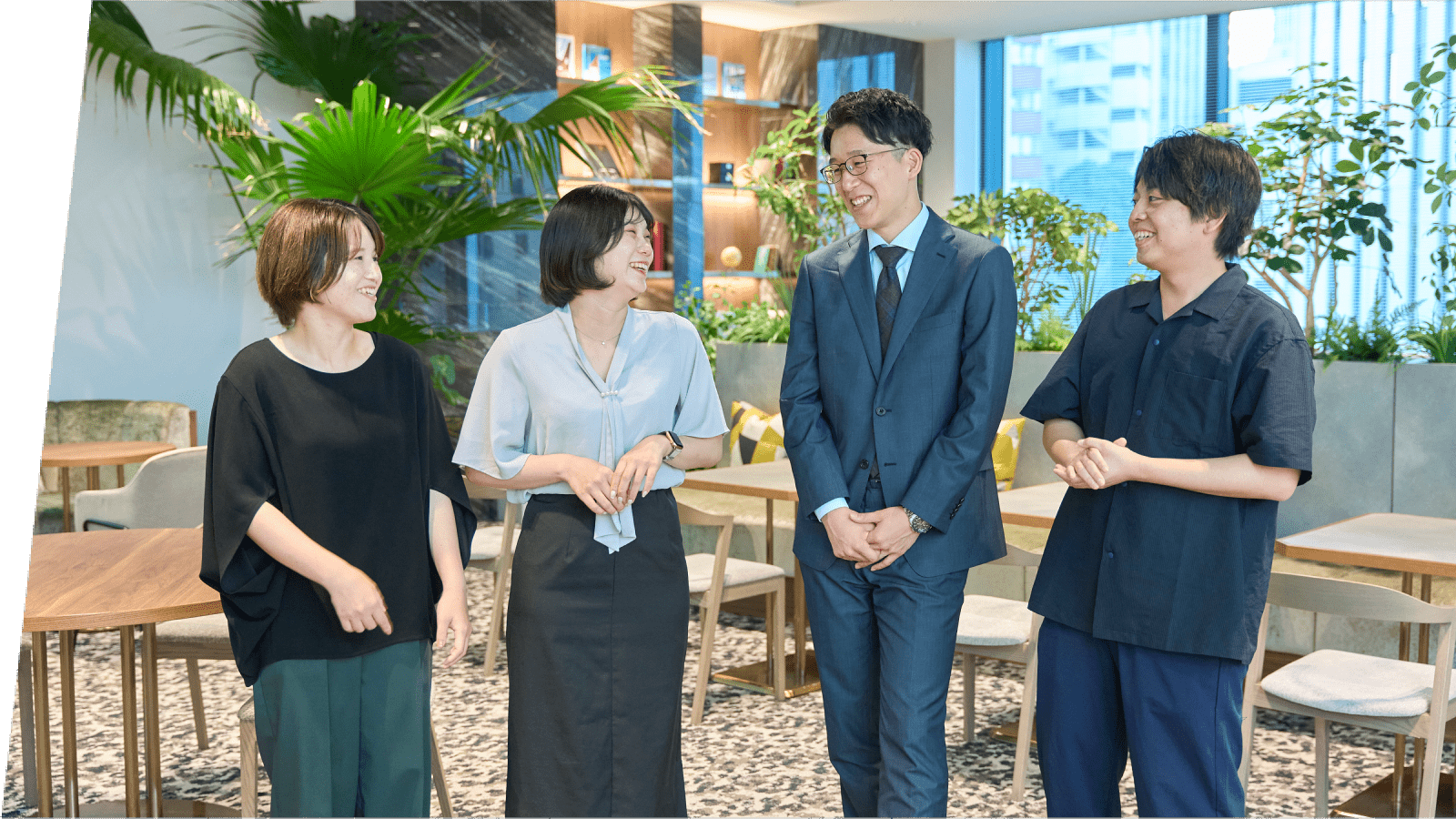
佐々木ファシリティマネジメント部は結構あるかも。部内の人と、突然ストレス発散会をしたり、夏休みの最初に年次が近いメンバーでドライブに行ったり(笑)。明日から頑張ろうという気持ちになれて良かったなあ。部自体が若手も多い明るい部署になってきていて、学校みたいな感じがする。
水高部署単位で遊びに行くのはうらやましいな…!渉外グループは、部署自体が小さいからグループ内で、というのは少ないかも。逆に色んな部署に助けてもらうから、仕事で関わった他部署の方と飲みに行ったり、大きな業務が1つ終わった時に労いの会を開いてもらったこともあって、楽しかったな。
中村部活動があるから、業務で関係は無くても、趣味で仲良くなるなんてこともあるよね。先輩が後輩を思いうかべる時に、部署じゃなくて部活の〇〇君、と言っている場面もある(笑)。仕事で一緒になった時も、業務で初めて挨拶するより部活で元々知っているという状態の方が、スムーズだよね。
水高分からないことがあっても、すぐ聞きに行けるようになりますよね。
自分はバスケ部に参加しているけれど、そこで仲良くなった先輩後輩と、休日にもバスケをしたり、バスケ観戦に行ったりもしていますよ!
佐々木社内イベントが定期的にあるのも良いですよね。参加したい人が参加できるときに、というスタンスだから、行くも行かないも自由だし、当日にいきなり「飛び入りで参加しなよ!」と言ってもらえることも。かなり幅広い年次の方との交流機会になるのが嬉しいです。
同期関連だと、2年目はよく同期同士で遊びに行っているよね?
下條本当によく遊んでいますね!普段は友達と変わらない感覚ですが、仕事においては困った時に助け合えるのでありがたい存在です。
Q